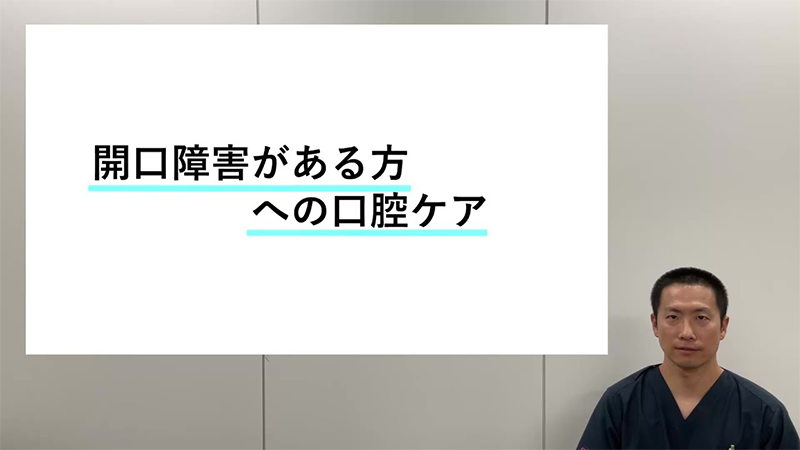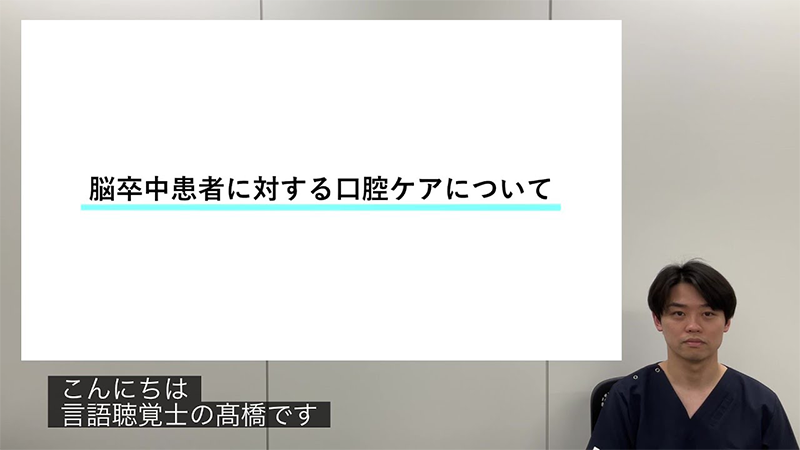-
小児期の口腔機能の発達にかかわる「口腔機能発達不全症」
[公開日:2025/5/9 /最終更新日: 2025/5/9 ]子どもたちと向き合う中で、最近特に気になっているのが「口腔機能」の発達についてです。むし歯は確かに以前よりも減りました。これは、口腔衛生に対する知識の向上等によるものであると考えられます。 しかしその反面、咬合や歯並びなどに課題を抱える子どもが増えているように感じます。今回は、そのような子供に関係する「口腔機能発達不全症」についてお話しします。
DENTAL HYGIENIST’S PROFILE

-
梅花女子大学 看護保健学部 口腔保健学科
教授・歯科衛生士
ながい るみこ
永井 るみこ先生
-

口腔機能発達不全症とは?
―保険収載された新疾患―
口腔の役割は「食べる」「呼吸をする」「話す」など生命維持に関わり、全身の健康にも影響しています。高齢者における摂食嚥下障害や誤嚥性肺炎の発症などもこの「口腔の機能」の低下に原因がある場合が多く、小児期に口腔の機能が発達・獲得し、高齢になるにつれてその機能は低下していきます。特に高齢者の場合、現在ではフレイル予防が叫ばれ、地域での介護予防事業に多くの方が参加されています。
これらの現実を踏まえ、2018年に「口腔機能発達不全症」「口腔機能低下症」の2つの病名が正式に公的保険に病名として収載されました。
現在、小児のう蝕は減少しており、本学科の歯科衛生士を目指す学生の口腔内もきれいな歯をした学生が多く、口腔衛生に対する知識の向上や生活習慣病としての疾患の予防や定期健康診査の普及の現れかと思います。しかし、その反面、咬合や歯並びの異常、口元が開いている子供たちが多くなっているように思います。
口腔機能発達不全症とは ※日本歯科医学会より
| 対象 | : | 初診時15歳未満の小児を対象とする疾患 |
|---|---|---|
| 病態 | : | 「食べる機能」「話す機能」その他の機能が十分に発達していないか、正常に機能獲得ができておらず、明らかな摂食機能障害の原因疾患がなく、口腔機能の定型発達において個人因子あるいは環境因子に専門的関与が必要な状態。 |
| 病状 | : | 咀嚼や嚥下がうまくできない。構音の異常、口呼吸などが認められる。患者には自覚症状があまりない場合も多い。 |
| 診断基準 | : | チェックリストによる評価診断 |
口腔機能発達不全症の対応方法
対応方法としては、①生活指導(姿勢改善や食事環境の見直し)②運動訓練(口の周りの筋肉や舌のトレーニング)などが歯科医院や自宅で行われ、改善に合わせてステップアップされます。
しかし、これら食べる姿勢や食習慣は、摂食・嚥下を獲得する離乳期が最も重要であり、その後もよく噛むことや食事の姿勢など成長に合わせて進めていくことが大切です。
食べる喜び、話す楽しみがすべてのライフステージにおいて営めるよう、う蝕や歯周病を予防し、歯科医院での定期健診をうけ、QOLの向上に努めましょう!!